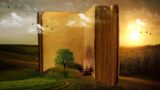今回の記事では行政書士試験の基礎法学対策法についてお話したいと思います。
特に独学で受験しようと思っている方はぜひ読んでみてください。
行政書士試験において基礎法学は重要性が低い
行政書士試験において基礎法学は2問出題されます。
2問ということはつまり8点です。
300点中の8点です。
他の科目に比してかなり重要度が低いと言わざるを得ません。
また基礎法学に関しては、対策法らしい対策法がありません。
一応その名の通り法学の基礎・基本に関しての問題が出るのですが、出題範囲が特に決まっているわけではなく、どのような問題が出るか予測がつかないため、対策法らしい対策法がないのです。
どのような勉強をすれば基礎法学で得点を取れるのか、明確な答えがないのです。
特に勉強しなくていいかも
上記の配点の低さと合わせて考えると、基礎法学に関しては特に勉強する必要はない、ということが言えます。
ただ全く勉強しないというのも不安だと思います。
できることがあるとすれば
①オールインワンタイプのテキストの基礎法学の項を読む
②問題集を解く
この2つくらいでしょうか。
まず①から説明します。
テキストを読んで最低限を でも気休めにしか
オールインワンタイプのテキストには、行政書士試験に出題され得る基礎法学の知識を解説したセクションが収録されています。
オールインワンタイプのテキストとは下記のようなテキストです。
一般的な行政書士受験生が買うようなテキストです。
このようなテキストに含まれている基礎法学の項を読みます。
ページ数としては他の科目に比してかなり少ないです。
ただし注意してほしいのは、これらの項を読んだからといって気休めにしかならないということです。
上記でも説明しましたが、行政書士試験の基礎法学に出題される知識はその範囲が明確に決まっておらず、どのような問題が出題されるか予想がつきません。
テキストで説明される基礎法学の知識は、法学の基礎中の基礎のことを解説しただけで、本試験に出題される知識の説明をしたわけではありません。
本試験には本当に種種雑多な問題が出題されます。
テキストを読んだだけで本試験の種々雑多な問題に対応できるようになるわけではありません。
何も読まないよりはましだろうという程度です。
ですのでテキストを読むとしても、あまり過度な期待はしないようにしましょう。
問題を解いて基礎知識の定着を
②について解説したいと思います。
②に関しても勉強したからと言って本試験での得点に直結するわけではないというのは①と一緒です。
ただ問題集を解くことで、基礎法学のトリッキーさに慣れることができます。
基礎法学の雑多さに慣れて、本試験で驚かないようにするのです。
どのような問題が基礎法学で出題されるのか、あらかじめ見ておきましょう。
また問題集を解いて法学の最低限の基礎知識を身につけておくことも大切です。
例えば、法の解釈方法(文理解釈、論理解釈)や法の効力(適用範囲など)辺りは行政書士の勉強をする上でも最低限身につけておいた方がいいです。
問題集を解いたからと言って本試験で必ずしも得点が期待できるわけではないですが、やらないよりはましです。
他の科目で学んだことを生かす
基礎法学に関しては他の科目を勉強していく過程で自然に身についていく知識を利用していくことも大切です。
民法や行政法、憲法などを学習していく中で、法学に関しての基礎知識はおそらく自然と蓄積されていくと思います。
例えば六法の条文の読み方などがそうです。
「又は」「若しくは」や「及び」「並びに」の違いをそれぞれしっかり理解しておきましょう。
こういった基礎中の基礎知識が問われる可能性も0ではありません。
他の科目の勉強中に得た細かい知識もできるだけ忘れないようにしましょう。
「又は」「若しくは」や「及び」「並びに」の違いがわからない方は、下記の記事を読んで学んでおきましょう。
「又は」と「若しくは」、「及び」と「並びに」の違いをわかりやすく解説
これらの知識は法律の勉強をする上で最低限身につけておかなければなりません。
「又は」「若しくは」、「及び」「並びに」の違いがわかっていないとまともに六法を読むこともできません。
できれば行政書士の勉強を始める前か、序盤の内にマスターしておいてください。
どうしても不安な人は
以上見てきたように、基礎法学に関しては対策法らしい対策法がありません。
配点もわずか8点なので、特別に勉強時間を割り振って対策するというよりは、他の科目を勉強中に得た知識を利用するという姿勢で臨むのが良いのではないかと思います。
どうしても不安だという人は、例えば以下のような書籍を読むのがいいのではないかと思います。
このような書籍を読んで、法の歴史、制度、用語についてピンポイントで勉強しておきましょう。
出題されるとしたらその辺りの可能性が比較的高いと思います。
ちょうど去年(2018年度)の試験では、世界の法の歴史と法の用語に関する問題が出ました。
新書なので読むのにそこまで時間がかかるわけではありません。
あくまで時間に余裕がある人向けですが、どうしても不安な人は、法学について基本的な部分から学んでみるのもいいのではないかと思います。
また以下の書籍も法律について基本的部分を学べる書籍として評判が高いです。
こちらの書籍は特に法律用語、条文の読み方を学ぶのに向いています。
またこの本では各法律(行政法、民法など)の勉強法についても学べるので、試験勉強の前にそういったことも知っておきたい方は読んでおくのがいいでしょう。
基礎法学の勉強法まとめ
行政書士の基礎法学は、配点が8点と重要性が他の科目に比べて低いです。
その範囲も非常に広く、対策を打つのが非常に困難です。
基礎法学に特別に勉強時間を割り振るというよりは、他の科目を勉強中に得た知識を利用するのがいいでしょう。
法律を勉強していく中で法学の基本的な部分について気になったことがあれば、積極的に調べるようにしましょう。
そういった細かい知識が本試験で出題されることがあります。
勉強するとすれば法の歴史、制度、用語といったあたりです。
あまり深入りする必要はありません。
基礎法学に割り振る勉強時間はほどほどにして、他の重要科目、例えば行政法、民法辺りを集中的に勉強しておきましょう。
それではまた。
他の科目の勉強方法、おすすめテキストを知りたい方は以下の記事へどうぞ。それぞれの科目で高得点を取る方法を解説しております。
行政法の勉強法、おすすめテキストを知りたい方は以下へどうぞ。
民法のおすすめテキスト・参考書を知りたい方は以下へどうぞ。
商法・会社法の勉強法、おすすめテキストについては以下のリンクで解説しています。
憲法はこちら。
一般知識はこちら。一般知識は非常に厄介な科目ですが、対策法を学んで足切りを回避しましょう。